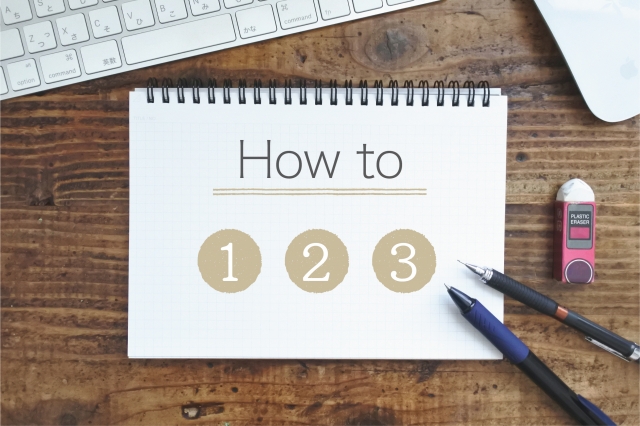フリーランスとして独立したエンジニアにとって、「節税」は避けて通れないテーマです。 案件単価が上がるほど、所得税や住民税の負担も増えるため、適切な節税対策を取ることで手元に残るお金を大きく変えられます。 この記事では、税理士の視点から、フリーランスエンジニアが今すぐ実践できる節税対策を初心者向けにわかりやすく解説します。
1.青色申告を活用して最大65万円の控除を受ける
フリーランスとして節税を始めるうえで、まず取り組むべきは青色申告の導入です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告を選ぶことで次のような節税メリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 家族への給与を「青色専従者給与」として大きく経費にできる
- 赤字の繰越控除(最大3年間)が可能になる
青色申告の控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けと貸借対照表の提出が必要です。 クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウド・弥生オンラインなど)を活用すれば、仕訳入力も自動化され、初心者でも簡単に対応できます。
まだ開業届を出していない方は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を同時に税務署へ提出しましょう。これがフリーランス節税の第一歩です。
※「青色申告承認申請書」は提出期限が決まっています。早めに提出しましょう。
2.経費を正しく計上して課税所得を減らす
フリーランスエンジニアの節税の基本は、経費をもれなく計上することです。経費とは「事業のために使った支出」のことで、所得(課税対象)を減らす効果があります。
主な経費の例
- パソコン・モニター・周辺機器:業務で使う機材は全額経費(10万円以上は減価償却)
- ソフトウェア・SaaS利用料:GitHub、Adobe、Notion、ChatGPTなども対象
- 通信費:自宅のWi-Fiやスマホ代は業務利用割合で按分
- 交通費:打ち合わせ・取材・勉強会の交通費やガソリン代
- 交際費:取引先との食事や勉強会後の懇親会費用
- 在宅ワーク関連費:自宅の家賃・光熱費の一部を経費化可能(按分計算)
節税のポイントは、領収書・請求書をすべて保存することです。電子帳簿保存法の改正により、PDF・メール明細も電子データで保存すればOKです。 クラウド会計ソフトと連携して自動でデータを保管するのもおすすめです。
3.iDeCo・小規模企業共済で「将来の退職金+節税」を両立
フリーランスエンジニアが今すぐ活用すべき制度が、iDeCo又は小規模企業共済です。個人事業主のための「退職金制度」のようなものです。
- 月1,000円〜70,000円(iDeCoは上限6.8万円)まで自由に掛金を設定できる
- 掛金は全額が所得控除の対象になる
- 将来「退職金」として受け取れる
たとえば、月3万円を掛けると年間36万円の所得控除が受けられます。税率20%の人なら、年間7万円以上の節税効果が見込める計算です。 しかも、将来「退職金」を受け取るときも、退職所得や公的年金として税制優遇を受けられます。
デメリットとしては、原則として中途解約ができない点が挙げられますが、長期的な資産形成と節税の両立を考えるなら非常に優れた制度です。
4.ふるさと納税を活用して所得税・住民税を減らす
個人で使える節税制度として、ふるさと納税も欠かせません。
ふるさと納税
ふるさと納税は実質2,000円の自己負担で全国の自治体に寄付ができ、所得税・住民税が控除される制度です。Amazonギフト券などの返礼品をもらいながら、税金を減らすことができます。
確定申告が必要なフリーランスの場合は、寄付した自治体ごとの受領証明書を添付して申告します。年末にまとめて寄付するよりも、年の途中から分散して寄付したほうが控除上限を計算しやすいです。
5.法人化(会社設立)による節税の可能性を検討する
フリーランスとしての所得が増えてきたら、法人化(会社設立)も選択肢に入ってきます。 一般的な目安は、年間課税所得500万円〜1,000万円程度で検討するのが理想です。
法人化のメリットには、次のようなものがあります。
- 給与所得控除が使える(個人より税率が下がることが多い)
- 家族に給与を支給し、所得を分散できる
- 社会保険加入により老後の保障が手厚くなる
- 法人特有の節税策が使える(社宅活用・出張旅費・社用車など)
ただし、法人化には登記費用や税理士報酬、社会保険料など新たなコストも発生します。節税額とコストを比較して判断することが重要です。税理士に「法人化した場合のシミュレーション」を依頼すれば、数字で有利不利を明確にできます。
6.節税で失敗しないための注意点
節税を意識しすぎて「経費を無理やり増やす」「実態のない出費を計上する」と、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。あくまで業務と関連性のある支出に限定するのが鉄則です。
また、クラウド会計に頼りすぎず、毎月の売上・経費・利益を自分で把握しておくことが経営者として重要です。定期的に税理士と打ち合わせを行い、最新の税制改正や控除制度を確認することで、より確実な節税が可能になります。
7.まとめ:今日から始めるフリーランスエンジニアの節税習慣
フリーランスエンジニアが節税を考えるときに大切なのは、「正しく」「継続的に」取り組むことです。節税は一度きりのテクニックではなく、事業運営の一部です。
今回紹介した5つの節税対策をまとめると次の通りです。
- 青色申告で最大65万円の控除を受ける
- 経費を正しく計上して所得を減らす
- 小規模企業共済・iDeCoで退職金+節税効果を得る
- ふるさと納税で所得税・住民税を軽減
- 所得が増えたら法人化を検討する
これらを実践することで、手元に残るお金を増やしながら、将来の資産形成にもつなげられます。節税の第一歩は「数字を見える化」すること。会計ソフトや税理士を上手に活用しながら、賢いお金の管理を始めてみましょう。
法人化等の無料相談は「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。